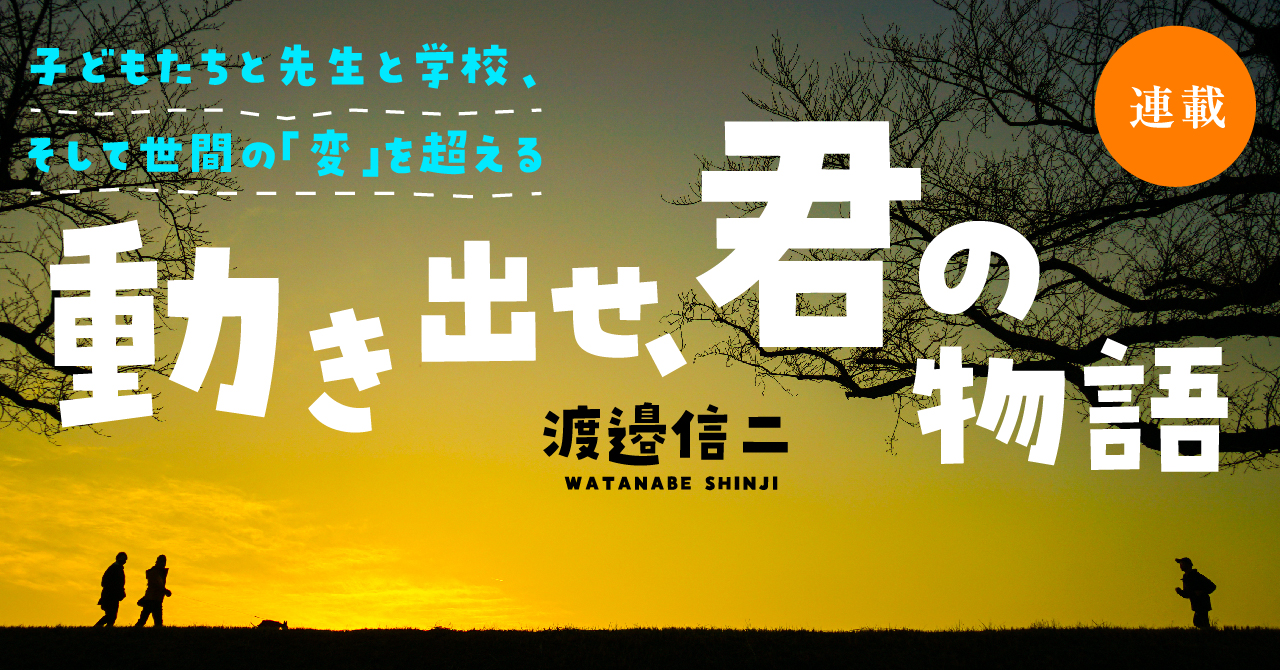小林怜巨さんと語り合う
“ 教室の学びは、時と空間を超えてゆく ”
はじまりの「言の葉」
ぼくは、小学生の学ぼうとする気持ちに、少しばかりの焰のようなものを灯す仕事をしています。そしてその灯りを感じて、実はぼく自身も密かに立ちあがってゆくこころをいただいている次第です。ひとというのは、ぼくを筆頭にして誰かに何かをしてあげているなんて思いあがっているけれど、実は「お互い様」なのかもしれないな、と実感することはありませんか? 近頃、この「お互い様のこころ」の気配が薄れていることがとっても気になります。端末の中ではたくさんの「いいね」が飛び交っているのにもかかわらず、空気を介した息遣いや視線が交わる世界ではどうでしょうか?
この連載では、ぼくの経験や実践の中で湧き水のようにこころの内に沁み込んで、いのちを支えるもとになっているような事柄たちを少しずつ取り出してみようかな、と思っています。それは、ぼく固有の経験のように観えて、実は隣のあなたにも重なり響き合う“味”をもっているように思えます。ぼくの教え子さんたちやその家族のひとたち。授業で出逢った街のひとたち。ぼくに大切な事を手渡ししてくれたひとたち。本や美術や音楽などのぼくの“先生たち”。“先生”の中には、喪失体験という悲嘆や苦しみもあります。そんなことを懐かしい再会や対談の力もかりつつ、書き綴ってゆけたらいいな。そうしたら、お読みになるあなたの「あの時」「あのでき事」と交差点を結べることもあるかもしれません。そんな「ひとりの誰か」と響き合うことを希求して、小さな“居場所”を拵えてみたいと思っています。今回の対談の相手は、高校2年生の小林怜巨さん。ぼくがかつて受けもった小学校6年のクラスの教え子です。語り合いは、「デジタル時代に求められる対話って何だろう……」というところに進んでいきます。
あいさつ運動を疑う
渡邉 あのころの、あの1年間だけだったけど、すごく凝縮した時間だったと思うのよ。あの時間がね。小林さんをはじめとして面白いひとたちがいっぱいいてさ。それで今ふと思い出したんだけど、中学の時に悩んで電話してきたことがあったじゃん。悩むっていうか、疑うというか、ケチを付けるというか。あいさつ運動だったっけ。
小林 そう。少し違和感を覚えたんです。中3の時の夏の作文で、あいさつ運動って何だろう、あいさつ運動って何のためにやるんだっていうのを書いたことがあって。あいさつっていうのをルールにするのがすごい嫌だった。ぼくは、あいさつっていうのはキャッチボールだと思っていますから。
渡邉 そうだよな。
小林 コミュニケーションの一種だと思っているのに、それを定型文のごとく、おはようございます、おはようございますってやっているのは、人工知能と一緒。ペッパーくんが「おはようございます」とか言って、校門の前でこうやってペコっとやっているのと全くもって同じことをしているだけ。
渡邉 それ、面白い話。確かに確かに。
小林 それをただ人間がやっているっていうだけだと思うんです、あいさつ運動っていうのは。たぶん今でも小中学校で、委員会とかPTAとか、そういう方々が中心になってやられている活動だと思いますが……。
渡邉 その感覚、すっごくわかるんですよね。何か引っ掛かるんだよね。違和感というか。疑うよね。
小林 実際やってみても、じゃあ、あいさつの機会、増えますかって言ったら、はっきり言って増えないんです、あんなことしたって。
渡邉 何がそうさせているんだと思う? だって、あいさつしようしようって言っているわけじゃん、学校ぐるみで。それなのに、そのあいさつ運動がなくなった瞬間に途切れるというのは何でだろう。人工知能と同じって言った言葉が、すごく印象的なんだけどさ。要するにプログラムするひとがいなくなっちゃう(校門で呼びけるひとがいなくなる)と、もともとあいさつの意思がないひとはやらないってことだよね。
小林 そうそう。やらないっていうことです。
渡邉 変だよな、それ。
小林 だからほんとうに、今の時代、あいさつをここでしておいてくださいって言えば、人工知能はそれぐらいならできるわけじゃないですか。
渡邉 できる。プログラミングされているんだから。
小林 それを人間にやらせるっていうことが、すごく不可解。
渡邉 そういうことを聞いてくれるひと、当時、ひとりでもいた?
小林 いや。
渡邉 たくさんいなくていいと思うんだけど、ひとりでもいれば。
小林 少なくとも先生方の中にはいらっしゃらなかった。
渡邉 いなかった。じゃあ、生徒は?
小林 生徒の中では、それこそ同じ小学校から上がってきた子とかの中では、確かに言われてみればそうかもっていうふうに言ってくれる子はいました。でもやっぱり少数っていうのがかき消されるような社会。あとは、取りあえずこれにしとけばいいんじゃね? みたいな無難なやり方にこだわろうとする、そういう姿勢は感じるので。明らかな批判というか、明らかに「これはいかんだろ」みたいなことを言うひとはほとんどいない。結果的にこっちの方が無難だし、こっちの方がよくね? みたいな。
渡邉 無理しないよね、今はね。
小林 そうですね。
渡邉 社会というか世間全体が無理をしないような気がするんだ。
小林 そう。それが、もちろん良く働く時もあるかもしれない。でも変化っていうものは全く現れないわけで、無理しないっていうのは。
渡邉 それは何? やっぱり浮いちゃいけないと思っちゃうの?
小林 まあ、それもあると思うし、やっぱり他人に関心がないからかな。
渡邉 コロナの時代には、マスクに閉ざされたっていうのもあったかな。
小林 まあ、それもあったと思う。
渡邉 マスクの影響っていうのは、なかなか難しいと思うんだけど、毎日していたマスクの影響って、学校生活の関わり合いの中で、どんな点で出たと思う?
小林 やっぱり口元が見えなくて、目でしか表情が見えないっていうのは、何て言うんだろうな、SNSでポンポンとメッセージ上でやり取りしているのと大して変わらないんじゃないかなと。
渡邉 「目だけ」だと?
小林 そう。視覚的な情報がひとつ減るだけで、こんなにも相手の気持ちって分からなくなる。マスクの生活ってある意味ですごく面白かったなって思っています。もちろん不自由な点もありましたし、やりづらいなっていうこともあったんですけど。でも正直、人類がこれまで数千年間、数万年間、人類というものが誕生してから、口元が見えない生活っていうのが、こんなに2年もの長い期間あったていうのは、これまでに日常ではなかったと思うんです。でも、ぼくは、生きている間にこういうことを経験して、逆によかったなと思っていて。
渡邉 何がそう思わせるの? よかったって。表面的にはすごく閉ざされていたわけじゃん。分断されているわけでしょ?
小林 そうですね。
渡邉 何がよかったって言わせるのかな?
小林 何て言うんだろうな。難しいな。
渡邉 経験できないことができたってこと?
小林 まあ、それはそうですね、ひとつあると思う。
渡邉 経験できないことができたことの中のひとつに、ちょっと絶望的な嫌なことっていう経験があるわけじゃない? 何て言うの? 都合が悪い? 都合が悪くないことはある? そこから学び取れることとか。
小林 都合が悪くないこと。そうだなあ。何だろうなあ。
渡邉 気づきとか発見という意味で。
小林 口元が見えないっていうことが、何て言うんだろうな、おまえほんとうにそう思ってんの? とかいう時に、少し笑ったりしたりとか、ニヤッとしたりとか。おまえ、実際うそついているだろって、ニヤッとしていても、マスク付けていたら分かんないわけで。
渡邉 そうだよ。感触で分からない。たとえば人工知能が「あなたのことが心配です」っていう字面をポーン出してくるのと、「俺さ、おまえのこと心配なんだ、ずっとさ」っていう生身の言葉の、息づかいの声って。それがないのとあるのって、何が違うの? だって同じこと言っているわけじゃん。「あなたのことが心配です」って言うのとさ、「俺さあ」って、口元が見えて表情がある中でそれを伝えるのと、そうじゃないものの違いって何なの? 字面は同じじゃん。決定的なことじゃない? これって。何が違うのか。
小林 例えば抑揚とかで言えば、声が大きくなったり小さくなったりっていうのは、たぶん先生とかも、それは学校生活の中で、すごく感情的になるシーンだと声が大きくなったりだとか、逆に声が小さくなる時もある。同じ感情的になる中でも、声が大きくなるところと、声が小さくなるところに、そこに注目すると、何て言うんだろう、違いというか。何て言えばいいんだろうな。
渡邉 面白いよ、その話。例えばさ、渡邉信二が感情的になった時にすごく大きな声出して張り上げて言う場合と、わざとささやくように言う場合があるっていうプログラミングをして、人間型のAIがそれを再現しようとした場合。再現できないものって何だと思う?
小林 例えば泣くとか。
渡邉 じゃあ、「泣く」もプログラミングしちゃう。行為として出てくるよね。大きい、小さい、泣く、みたいなのが出てくるよね。それを再現することって可能じゃない? でも、実際のぼくと何が違うの?
小林 何が違うのか。う~んなるほど。
渡邉 難しく考えなくていいと思う。決定的に違うものがある、AIとぼくとで。俺って何だっけ。人間。あ、言っちゃったよ。俺、ひとじゃん。AIって何だっけ。
小林 AIは機械。
渡邉 モノでしょ。だから、どんなにプログラミングとかテクノロジーが発達しても、モノは絶対モノなんだよ。もしかして心というものが発見できて、心というものをAIがやったとするよ。心を漢字で書くのか片仮名で書くのか分かんないけど、俺なんか嫌みだから、AIの心なんか片仮名でしか書くつもりないけどさ。その時に、俺、絶対人間の心とは違うと思うよ。だってモノなんだもん。どんなに進化して進歩しようが、モノはモノだよ。そこの決定的な違いって、もう理屈抜きなんだよね。AIが泣こうが何しようが、俺が泣いているのとは違うんだよ。だってプログラミングで泣いているんだもん。泣けっていうボタンで泣いているんだもん。俺、誰にもボタン押されてないよ。だから、俺は別に争う必要ないと思っていて。AI対人間みたいによく対比するじゃない、でも全然別モノだから、戦いにならないと思っているわけね。でも、面白いね、あいさつ運動が人工知能と同じっていうのは、これ、大胆だな。でも、確かにそうだな。
小林 だって、あいさつしてくださいって、まさにプログラミングですよね。
渡邉 結局、あいさつの声がないっていうことが心配だったわけだよな。誰が心配だったかっていうと、教員が心配だったわけだ。何で心配なんだろうな、あいさつがないと。自分が嫌われていることが嫌なのかな。
小林 それもそうだと思うし、生徒が元気か元気じゃないかっていう、そこの物差しがあいさつでしか測れないから、現状、先生たちが。
渡邉 鋭い(笑)。
小林 日々の発言だとか日々の行動だとか、そういうところまで目を配るのって、もちろんとても大変だと思うんですよ。それは分かるけど、ただあいさつという一観点で、生徒が元気なのか元気じゃないのかっていうのを判断している。「今日はこの子がおはようって言ってないから、この子は元気じゃない。大丈夫かな」っていうふうに、あいさつだけで、こいつが元気か元気じゃないかっていうのを見分けようとしているから。
渡邉 門のところで「おざーっす」とか言われると嫌だな。ぼくは嫌だもん。しないもん。ぼく、「おざーっす」って言わないよ。いいじゃんな、静かでな、別にさ。あいさつなんてひとによって全然違うって。ある小学校で、学校に来るとしゃべれない女の子がいたのよ。ところが、その子のノートを見るとすごく書いているんだよ、意見とか。字も独特でさ。ああ、この子は言葉がないんじゃなくて、ただ音声言語として声が出せないだけなんだなと思った時に、「この子はしゃべれないんです。何も考えもってないんです」じゃないんだなってすぐ分かったわけ。だから、全然無理強いもしなかったし。あいさつも、ぼくの「おはよう」と言う声に対して、視線をまじらせ、コクンと頷く仕草を返す。もうそれで十分。それを一律に、声出して元気にあいさつを返さなきゃいけないみたいなのは、まさしくプログラミング。何の変化もない一律の決まりごとじゃん、そういうのって。何でそういうの、学校の教員は気付かないんだろうね。
小林 何でなんだろう。

多数決を深める
渡邉 あいさつ運動以外にも何かあった?
小林 何か不可解な点ですか。
渡邉 何か引っ掛かったところ。
小林 そういえば、今はみんな長時間の話し合いをすごく嫌いますよね。
渡邉 嫌う?
小林 話し合いを1時間で終わらせることに価値があるみたいな。例えば委員会とかで話をしている中でも、長時間かかってしまって話し合いが延びるっていうのは、それは時間の管理ができてないからだ、みたいな捉え方をすることももちろんできると思うんですが、でも、じゃあ、何で話し合いしているの? 話し合いをする理由っていうのは、あくまでお互いに意見をぶつけ合ったり、あるいは交換し合うことで何か学びを得て、そこから新しいものを何か生み出そうよっていうのが、話し合いの本来の目的なのに、それを今回は1時間で終わらせましょうっていうのは、1時間で終わらせることが一番の目的になってしまっている。もちろん、ひとつの話題に何日も、何週間もかけるべきとまでは思いませんけどね。
渡邉 違うよね、それね。
小林 何か結論を出すことじゃなくて、1時間で終わらせましょうっていうのが決まっているから、1時間終わったら、じゃあ、そろそろ結論をまとめていこうかって言って、ばばばってまとめて、最終的には多数決とかっていう、無難かつ少数派を無視するような手段を使って物事を決めて、じゃあ、来月はこういう方針でいきましょうみたいな方針を立てちゃう。
渡邉 1時間でやらせようとしたいなら、1時間でたくさんのものが出し合えるような方法を教えてくれればいいよね。でも、教えてくれないだろ。
小林 やんないわけで。
渡邉 そこが一番大きな問題だと思う。ぼくは君たちの時にもやったよな、「スタンドアップぐるぐる作戦」。
小林 ああ、やりましたね。
「スタンドアップぐるぐる作戦」とは?
ひとつの課題に対して、クラスの全員が立ち上がって順番に感想や意見を言い合う取り組み。感想や意見は「タイトル化」したり「ショートフレーズ化」して述べます。短時間で全員の動向が混じりあうことが可能な方法で、長時間の「深め合い」の前の段階で、広げたり俯瞰したりするのに向いています。自他の共通点や違いを視線や呼吸を交わらせて行うライブ感に富んでいる方法。一回一発言。ぐるぐるを繰り返して複数の感想や意見があるひとは二周目、三週目で発信。繰り返しのなかで発言者は絞られていき、意見や感想はふるいにかけるように活かされていきます。
渡邉 あれは、ショートパスをどんどんつないでいくやつで、タイトル化したり短くしたり、工夫もしたじゃん、俺たちには、それが、必要だった。何時間もかけて、全部の課題をやるわけにいかないんだけど、でも、あるひとつの課題について、ちょっとタイトル化してみようとか、キャッチコピー化してみようとかってやってみると、いろいろなひとがしゃべる。で、それを何周も回すっていうのをやったじゃん。ああいう方法って教えてくれる先生っていた?
小林 いないです。
渡邉 うん。いないなあ。
小林 すごく受動的というか、自らやろうとする能動的な行動っていうのが、小学校から中学校に行ったら、ものすごくガーンと減るんですよ。
渡邉 でも、「主体的な学び」とか言ってるんだぞ、文部科学省が。聞いたことあるだろ。対話的で深い学びとか、主体的な何とかって。だから、言うならちゃんとやろうぜって話なの。ない? なかった?
小林 ないです。
渡邉 片鱗もなかった?
小林 全くないです。
渡邉 何でだろうね。
小林 無難が一番いいと思っている。無難 is justiceだと思っているひとがいっぱいいるから。
渡邉 それでいて、SNSで平気でひとのことを中傷するんだろ? おかしいよな、そんなのな。
小林 そうですね。
渡邉 舞台でやれって話だよな、ちゃんとな。表舞台でな。でも、裏舞台でやっても同じように言っているやつがいるから、自分だけじゃないから気が大きくなっているっていうのは、やっぱりそこには多数決の原理が生きちゃってるんだよね。そこでもね。昔さ、多数決でやったあとに、必ず少数派にもう1回意見言わせようっていうのは教えたよね、俺。覚えてる?
小林 はい。
渡邉 その上でもう1回、決を採るよって言ったよね。必要だと思うけどね。
小林 意見が変わるひとがいるんですよ、あれで。
渡邉 意見が変わるよね。
小林 はい。何人かは気付かされて、やっぱりこうかもって思って、何人かは意見が変わることって全然あるんです。
渡邉 変わるでしょ。そうすると、その日の放課後にクラスの決議をもち寄る代表委員会とか生徒会があるなら別だけど、そうでなければ「さっき数人の意見で変わったじゃん。もう一晩、考えてきてくれないか」ってみんなに言いたい。ぼくが教員だったらやるべきだと思うのね、状況を見て。数人の意見でも影響力があるんだ。だから、今さっきの意見でこれだけ意見が変わるってことは、もうちょっと考える必要あるんじゃないかっていざなうことが、言っても仕方ないって諦めるひとを減らす方法だと思うんだけど、その辺どう思う? 諦めちゃうんだよ、結局。どうせ1時間で終わりでしょとか、俺がしゃべると長くなるから言うのやめようとかっていうひと、いるはずだよ。
小林 「まあ、でも、時間内で終わらせることも、ひとつ大事なスキルだから」と言われたり。
渡邉 スキル?
小林 「それも成長する上で、君が社会に出ていく上で大事なことだから」、とか。
渡邉 出たー。社会に出ていく上で大事なこと。
小林 「だから、今回は、君の意見を聞きたい気持ちも、君の意見を踏まえてもう1回話し合いたい気持ちも分かるけど、今回はそれで」みたいな。
渡邉 分かるならやってくださいって。
小林 「それで勘弁してくれ」みたいな、そんな感じだったんで。
渡邉 勘弁してくれっていう気持ちも分からないでもないんだけど、もうちょっと頑張ってほしいな。そのギリギリの線でな。社会に出る上で大事だとかいうの、もうちょっと違うところで大事なところがあるんだけどって、言いたい場面はなかった? やっぱり。社会に出る上で大事だって先生は言うけど、これは大事じゃないんですかって思うことはなかった?
小林 それこそぼくが言ってることって大事じゃないの? という場面……。
渡邉 それは言ったことある?
小林 あります。
渡邉 そしたら? 黙ってた?
小林 いや、でも、時間を守るほうが大事じゃない? みたいな。
渡邉 先生の生きるための指針とか、先生の魂にあたるような柱を取り壊してまでも、時間を優先するんですかって。そんなこと言えないよな。
小林 そこまでは、当時のぼくには言えなかったですね(笑)。
渡邉 でも、これから言いそうだね。
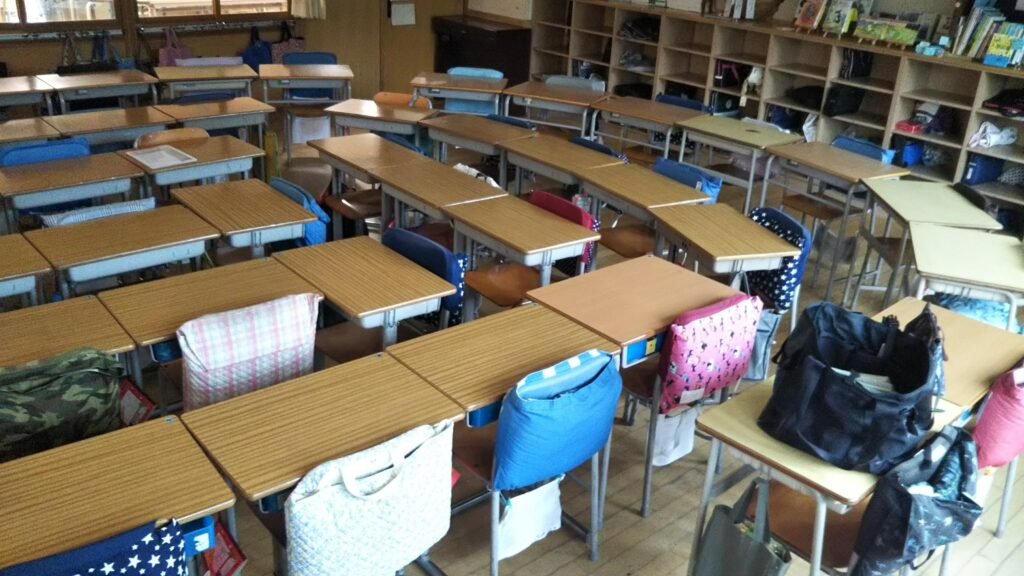
手触り感覚
小林 ぼくたちぐらいの年齢からは、生まれた時点でデジタル端末に触れている。もしかしたら、ぼくよりもちょっと後ろの世代ぐらいからかもしれないですけど。今はほんとうにすごいですからね。ちっちゃい子とか、ベビーカーに乗っている子ですら、スマホで「アンパンマン」見たりしていますからね。ほんとうにすごいなって。
渡邉 すごいよな。あり得ないよ。
小林 家でテレビで見ていたものが、もう手元のこの画面で見ることができちゃう。文科省のGIGAスクール構想について、ぼくはそんなに否定的な感じはありません。正直、まだまだ見出せていない活路もあると思うし。あとは、何て言うんだろうな。同じものに書き込めるとか、便利なことが多いので、ぼくはそんなに不自然には感じていません。実際にぼくが渡邉先生のクラスで小6の時に、対話しながら黒板に何か紙をはっつけたりしながらやっていたことと同じじゃないかなと思う。だからそんなに違和感なくぼくは受け入れられています。
渡邉 それは、君が本質を見抜く力があるからだと思う。見かけは変わったけど、やっていることはあの時と似ているなっていう感覚があるわけじゃない?
小林 それこそ今ぼくが小6に戻って、渡邉先生の授業を、今の環境で受けたとしたら、配られた端末に何か書き込んだりとかできると思う。だけどぼくの高校でもiPadがひとりに1台ずつ導入されているんですが、実際には使いきれていないような気がします。
渡邉 それは何かって言ったら、もともと対話的な授業をやっていないのよ。ぼくが今すごく危惧しているのは、いろんな小学校に行くでしょう。そうすると学校評価っていうのがあるんですよ。その学校評価の項目のひとつに、「対話的で深い学び」っていうのがある。これをGIGAスクール構想に重ねて評価する場合が多い。例えばひとり1台の端末を生かしながら、「対話的で深い学び」を実行できているかどうかを、レベル1~5で判定する。ところが、コロナの時代になってから教員になったひとって、直接息とか視線が交わったところで、子どもたちが混じり合ったような授業の力量がないなかで、いきなりGIGAスクール構想に入っちゃっている。「クラスルームやロイロノートに載せといてね」とか、「クラスルームやロイロノート、自由に見ていいよ、他の友達のも」みたいなところが、対話的で深い学びだと思っちゃっているわけ。ぼくはそれがすごく怖いと思う。君は小6の体験があるから、元があるから、ちゃんと対話を知っているんだよ。ところが、今はあれが対話だって言っちゃっているんだ、それがすごく怖い。
クラスルームやロイロノートとは?
ギガ端末上につくられた、子どもたちの感想や意見を集約する「場所」。自他の比較・関係付けを可能にしようとしてつくられたものなのだろうと思いますが、空気を介在できる空間(すぐ隣に)に相手がいるのに、個々が視線を下に落とし、コメントを送り合ったりするのは、ほんとうに有効な活かし方を考えないとおかしなことになるのは明白です。
小林 対話をはき違えているということですよね。
渡邉 はき違えている。だから、あれを使うことだけが対話的だと思っているんだ。深い学びだと。ぼくの答えはノーなの、それははっきり言って。
小林 それはぼくもノーだと思う。
渡邉 なあ? 危険だよな。で、今日ちょっと紙を使わないであれをやってみようかとか、でも、今日は紙でやろうぜ、ガチャガチャ言いながらやろうぜとかさ。
小林 何かそういう使い分けする必要はあるかもしれない。
渡邉 全然あると思うよ。だから、それを使うことそのものが、手段が、ツールが、何か願いとか目的とはき違えちゃっているところが多々あって、そこがヤバいですね。特に小学生はじかにやることが必要なのよ。手を使ったり、においを嗅いだり、まさに体を使って吸収するようなことが。それを小中学校とかって、国が一緒くたに塊で考えるもんだから。中学校と小学校って違うじゃん。中学生と小学生って。それはどう思う? 小中をひとかたまりで教育を考えちゃうのよ。すごい危険だと思うんだよ。ぼくはね、ひとりに1台の端末、小学生には要らないと思う。中学生からでいいと思う。それはどう思う? だって、別に学校がやんなくたって家でやっているんだからさ、端末なんか。それはどう思います?
小林 ひとりに1台の端末を必ず導入するという点は、ぼくも要らないと思います。対話だとか、ある程度そういうものの本質が分かった上でやるべきだと思うから。でも、具体的に何歳からやるべきとか、ぼくはあまりないんじゃないかなって。中学生でも対話ができないひとっていうのは山ほどいるし、高校生や大学生になってもたぶんいると思うし、何なら社会人でも、できないひとってたぶんいるんじゃないかな。だから、端末を使うことを強いる必要はないんじゃないかな。
渡邉 ぼくね、びっくりしたのが、ある小学校に行って見学していた時のことなんだけど、ちょうどタブレットをもった4年生の子どもたちが校庭に飛び出してきた。その学校は外周に樹木がいっぱいあるんですよ。名前も貼ってあって、すごくいいのね。昔に理科の先生がやったんだなと思って見ていたら、何かチャカチャカと来て、パチパチ写真撮っているわけ。ああ、撮っているなと思ったわけ。ところがそれですぐ戻っちゃうわけ。いなくなっちゃうわけよ。それで俺、ついていったの。何やってんの? 「観察しているんです」って言うから。でも、バンバン撮ってから、戻って何しているかといったら、スライドづくりしてるわけ。それで、スライドの切り替えの時のアニメーションの回転とか、楽しんでつくってんの。一見、“よくやっているように見える”わけ。“主体的にやっているように見える”わけ。
小林 ああ、そうそう。
渡邉 ところが、生き物の観察してないのよ、全然。ぱっと見て、ぱっと写真撮って、においも手触りも何もなくて、ぱっと来てぱっとやっているわけ。これってスライドづくりの授業? と思っちゃったわけ。言わなかったよ、先生には。どう思う? この話聞いて。
小林 人類の良さをつぶしていますよね。
渡邉 そう思う?
小林 人類の良さが人類が生み出した文明の利器によってつぶされてしまっているんですよ、それって。
渡邉 おかしいじゃん、それ。本末転倒じゃない?
小林 端末、タブレットとかパソコンとかの登場によって、人間がもちろんこうやって触って、においを嗅いで、それで得て、文字化できるところが、これが人類のいいところ、人類ができることなのに、それをパシャパシャ撮って、目で見たことだけの情報で、
渡邉 そこなんですよ。
小林 何か書いて、それでスライドをつくったり、リポートをつくったりっていうのにとどまっちゃっている。フィールドワークチックなことがないですよね。
渡邉 さっき「目だけ」って言ったけど、やっぱり視覚過剰だよね、今の社会全体がね。五感って5つもあるわけじゃん。においを嗅いだり、なめたりさ。
小林 コロナの頃には、マスク付けていたから、それできなかったんです。
渡邉 だから、マスクの怖さって、さっきもちょっと話になったけど、マスクで口元が見えなくて、目で見ただけのものって、すごく不十分だけど、その不十分さに慣れちゃって、何も思わなくなった。俺、よく麻痺ってことを言っていたじゃん。麻痺、怖いよって言ったじゃない? まさにそれだよね。でも、しびれすらも感じなくなっちゃってさ。いや、視覚だけで捉えているっていうか、視覚過剰っていうか、視覚偏重というか、これによって。俺、ほんとうにぞっとしたのよ、その理科の授業を見た時に。それで、俺、その学校で理科を受け持ったの、そこの4年生の。まさにその子たちを受けもったんだけど。子どもたち、分かるんだよね。におい嗅いでみたらさ、やっぱりやるのよ。その大切さを言うのよ。で、俺はあえてその時カメラはもっていかないよって、もう写真は撮らないよって。必要ならスケッチとかさ。でも、スケッチしなさいとは言わなかった。手触りなら手触りを書いてって言ったんだ。そしたら、擬態とか擬音が出てくるのよ。擬音語とか擬態語が出てくるの。もにょもにょしているとかさ。で、「あー」とか言うのよ、そういうのを小学校時代にスキップしてしまったらヤバいなと思ったんだよね。それは君ぐらいの年になったら、もういいと思うんだよ。でも、それも小学校の時にそういう体験を十分に積んだひとが、元があってさ、その元に対してっていうのができるわけじゃん。あの時はこれやってたけど、今回はロイロノートでやろうよとかさ。それがあるかないかって決定的な違いだと思うんだ。
小林 はい。小学生っていい意味でピュアだし、そういうところの感性がすごい豊かな時期でもあるし、ぼくも年を取って、そういうところが、そういう感性が薄くなったなっていう部分はすごく感じるので。ぼくも小学校を卒業して3〜4年が経って、たかだか16年、17年、生きた身ですけど、すごくそれは感じるので。小学生のときよりも。だから、12歳のときの小林怜巨よりも、全然そこの感性はめちゃめちゃ衰えたなって思うんです。小学生こそ、実際に触れて、子ども同士で対話してみたいな授業って、ぼくは必要だと思うんです。
(対談:2023年6月)
しめくくりの「言の葉」
タブレット端末のほんとうの使い方
ここまでの対談を一読すると、空気を介在したリアルな対話と端末を経由した対話とを比較して、優劣をつけているのかな? と思われる方もいるかもしれませんね。でも、着地点はそこではありません。ぼくが近頃特に危惧しているのは、“ちっちゃな大人”みたいな小学生を国ぐるみで育成して、同調圧力に弱い、ある立場からみれば従順なひとびとをそれこそ材料みたいな言い方の「人材」として大量に“生産”しようと何だかとても焦り過ぎているように感じ入ります。考え過ぎでしょうか?
ギガ端末は、もともと感染症の蔓延で、学習権を保証するための個別対応の手段でした。リモート交流の美点は、空気を介在できない遠隔地や個別のニーズなど、それこそ個別的な状況に応じられることにあります。
ぼくは、コロナ以前から、体育科の跳び箱運動の学習で観てほしい技の目当てポイントを告げてから試技をする際に、共同で学ぶ他のクラスメートが端末で撮影した映像を試技した本人と見合いながら、目当ての達成や課題について交流し合う場面でタブレットを活用してきました。もうずっと何年も前の話です。また、メダカの卵の成長の段階を理解し合うためにもタブレットを使った映像撮影や保存、提示は学び合いに有効でした。さらに、図工の鑑賞の授業「学校は美術館?」で、校舎内の壁や床、天井などに“作品”を視つけてタイトルをつくって巡ってゆくような営みでも、タイトルと場所を記入した一覧が端末上で確認できたら便利だと後々の「鑑賞ツアー」のことも含めながら思います。
「学校は美術館?」と「鑑賞ツアー」とは?
学校の校舎内の壁や天井、床、階段、棚などをよく観ると、形や模様や色、手触りについての「発見」があります。何かの顔に見えたり、生きものや様々な事物に見えたりするのです。すると、「題名」をつけたくなるものです。やがて、必ず校舎内には作品はあるのだ、という確信をもって見つけようとすると、「作品」の方からぼくたちを呼んでくれることさえあります。そうするとしめたものです。「ああ、学校は美術館だったんだ。作品だらけだよね」と呟きながら、見慣れた校舎が鮮やかな発見とともに再生されてゆきます。題名のラベルをその場所に添付したら、命名した作家のガイドで「鑑賞ツアー」の始まりです。鑑賞者たちは、自分だったらこんな題名をつけるよと言い合いながら、ツアーを交代しながら愉しんでゆくのです。
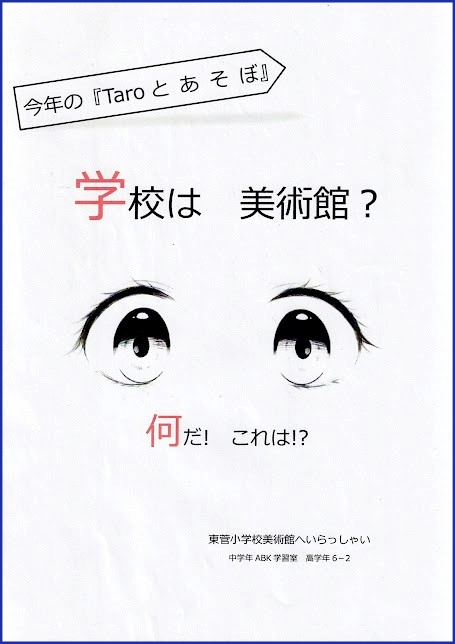
客観性と普遍性は異次元
ただ、それは情報共有や確認の領域である限り、他にも手段は考えられます。まさに「必要な時には活かす手段」としての選ぶ要素、選ぶ手段のひとつでした。だから、一律に「ひとり一台」という発想をぼくはまったくもっていませんでした。一律性や均一性は一見、見映えはいいのですが、「全体」とか「みんな」とか、「~ねばならない」という論調に流れやすくなることが多々あります。それは個々の必要感や自主性の育ちとは実は本質的にかけ離れているのです。また、「全体」という言葉が前に出てくると、個別的な経験の価値が、「客観性」という言葉によってかき消されてしまう怖れがあります。近頃使われている「客観性」は、ともすると「普遍性」と同義に語られる場合が多いように思います。たくさんの情報を収集して平均的な傾向を出すことが悪いなどとは言いません。だとしたら、それは、「妥当性」という言葉があてはまると思います。均一性や妥当性は、普遍性とは異次元です。
時と空間を超えて再生する
ぼくは、2010年にいじめによって自死に追い込まれた中学3年生の篠原真矢さんの極めて個人的な経験を調査によって模索しました。真矢さんがどう生きたのかという「生き方報告書」を希求することが肝心でした。ひとの弱さを排除し、支配するといういじめの核心から被害者を救済しようと試みた時、そこでは個人的な経験の極みとも言える領域にふれるということを知りました。そして、その他者性を抱きながらの「手当」は、誰にとっても通じる普遍的な価値や託を宿らせていることを学んだのです。個人がもつ個別的な体験を支援する「わたし」が、体験を経験として価値づけ、共に歩き出す営みをつくり出そうとする試みの中に、誰も置き去りにしないと強く決意する人間の意思が息づいてゆくように思えるようになりました。このような営みの本質に在るのは、うまく言えませんが、頭で考えると言うより、からだで丸ごと吸い込むような感覚の感度の鋭敏さを必要とするようにも思えます。
ぼくと小林さんはその点において、久しぶりに再会したにもかかわらず、瞬時に“シンクロ(共振)”することができました。これは、実は小さいことのように思えて、実に重要な気付きでした。ある一時期の教室の学びが、時と空間を超えてまさに再生したような感覚だったからです。学びが教室を飛び出して翼をもって羽ばたいてゆく可能性を示している、と言ったらちょっと大袈裟でしょうか? だから、小林さんとの再会は、単なる懐かしさを超えた不思議で有意義で、愉しい時間として呼吸していたのです。
※対談は次回に続きます。
1966年生まれ。川崎市の市立小学校教諭や、川崎市教育委員会学校教育部指導主事などを長く務める。教育委員会に在職していた2010年、いじめをきっかけに自死した市内の中学3年生・篠原真矢さんについて調査を担当。調査の結果を「死亡報告書」ではなく、彼がどうやって生きていたかを綴った「生き方報告書」としてまとめる。現場に復帰すると、自分の担任するクラスで篠原真矢さんのことを話し、独自の授業を展開。教室では、いじめられていた過去をもつ子、いじめていた過去をもつ子、いじめを黙認していた過去をもつ子たちが、やがて自分の内面を語りだし、自らの言動を省み、成長していく――その実践の模様はNHK for school「いじめをノックアウト」で再三紹介され、2020年5月6日のNHKスペシャル「“わたしをあきらめない”~5年1組子どもたちと先生の一年~」では、子どもたちとの日々を密着取材で紹介。このNHKスペシャルは英語化されてNHKワ-ルドでOA。タイトルは「Leaving No One Behind」(だれひとりとしておきざりにしない)と題された。2020年3月に早期退職すると、小学校の臨時教員や非常勤講師を受けもちながら、2021年に『最後まで読まれなかった「クリスマスの物語」――川崎市中学生いじめ自死事件調査報告書から』(高文研)を発刊。以来、「語り部:真矢さんのクリスマスの物語を読み続けるひと」として、全国の小中学校などでいじめについて考える講演を続ける。2024年4月リリースの「いじめ防止教育DVD『考え、議論する道徳』」(映学社)では監修を担当。三部作からなるこのDVDのうちの1本『いじめの構造を考える 孤立化 無力化 透明化』は、日本視聴覚教育協会主催の令和6年度(2024年度)の優秀映像教材選奨(教育映像祭)で優秀作品賞を受賞した。また2024年7月から、中日新聞のポッドキャスト「あしたのたね」で、いじめ問題の対処について被害者家族と語り合う対談が連続配信されている。